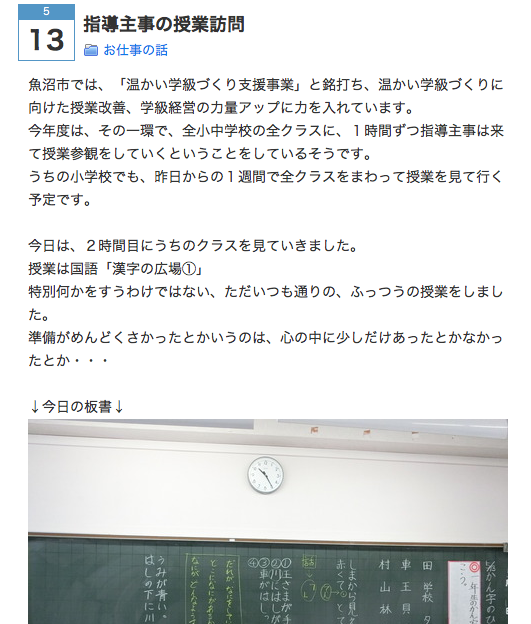「課題ボード」の効果
あなたは授業が始まった時に学習課題を黒板に書きますか?
あなたの同僚はどうですか?
あなたは学習課題を赤や青の線で囲っていますか?
あなたの同僚はどうですか?
あなたとあなたの同僚の「学習課題」のとらえ方は同じですか?
これらは違っていていいのですか?揃っていた方がいいのですか?
この問いかけは拙著「学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)」の「はじめに」の冒頭の文である。
なぜ、このような問いかけをしたかというと私は確信をもって
「学習課題は書いた方が絶対にいい!」
「あなたも同僚もみんなで書いた方が絶対にいい!」
「学習課題は全校、赤(青)で囲うことにした方が絶対にいい!」
「学習課題のとらえ方は全校で共通していた方が絶対にいい!」
と言えるからである。
課題ボードのない学校に転出した先生はだれもが言う。
「課題ボード欲しい。」
「自分で作ろうかな。」
「いちいち線を引いて囲むの面倒。」
一度、課題ボードの便利さを知ってしまうと、それなしでは辛くなる。
そして一旦定着した「学習課題を書く習慣」は失われることはない。
なぜなら、課題をしっかり設定した授業は安定して成果を上げられることを身をもって知るからである。
先週も紹介させていただいた、たらむりょう先生の小学校のせんせのほぼほぼ日記に、課題ボードの効果を示していただいた。
↑↑↑クリックしていただいたら記事に行きます。
たらむりょう先生の言葉を引用させていただく。
「めあて」の提示を確実に行うということで、黒板にマグネットシートを常駐させることで、教師側も強くめあてを意識できるし、子どもも学習しながら、「あっ、めあてはこれだった」と立ち止まって振り返り、進路を戻す姿も見られるようになりました。
教師も子どももねらい・学習課題を強く意識できるようになる。
これは体験してみないと分からない感覚ではあると思う。
白地に赤枠の「課題ボード」に向かい水性ペンを手にして、授業のねらいを学習課題として表現する体験をぜひしてみていただきたい。
子どもたちはそれをノートに写して、同じように赤で囲む。
そうやっていつも当たり前のように学習課題からスタートするのである。
同じように大切なのは、授業の最後に学習課題に対して子供たちが成果を上げられたかの確認(評価)である。
拙著には、課題ボードを使った授業の進め方、評価のしかたまで詳しく説明してあるので、興味のある方はぜひ手にとっていただきたい。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)
- 作者: 能澤英樹
- 出版社/メーカー: 明治図書出版
- 発売日: 2015/01/16
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る